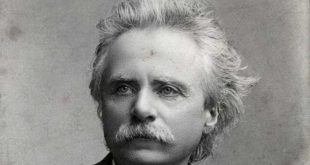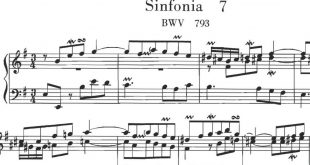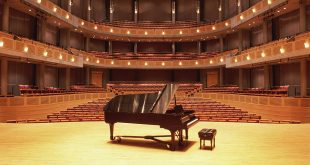マスネ作の美しい名曲を4回に分けて学んで行きます。今回は2回目。 前回に引き続きバイオリンと同じくらい豊かに歌う練習をして行きます。 3段目で戻ってくるテーマはpppです。冒頭のppより一層小さな音量で。 初めに比べてクレッシェンドなどの表現は抑え気味にフラットな感じで。 4段目の頂上で盛り上がるためにセーブしておきます。 タイミングも使ってまず急いで→ためてを繰り返しテンポを変化させます。 2pの3小節目の長いフレーズの終わりはたっぷりritで。 中間部の始まりはテンポを戻し、ルバートで揺らしましょう。 calmatoは穏やかに。dolceを経てまたテンポが速く強弱も激しくなります。 3連符は均等に弾くよりルバート気味にロマンティックに感じて表します。 右手のタッチは引張ってタイミングを意識。指は1235-2等スムーズに。 5-5421、5-5321なども一つの動きでレガートに。2声が歌える指使いで。 ピアノアレンジの曲は音楽が自然に流れるように指使いを工夫します。 左手は右の旋律を頭でイメージしながら自然なタイミングを練習します。 左右併せて音楽を自由に大きく表現できる様に腕も柔軟な動きを意識。 旋律が伴奏部と近い位置にある所は少しソプラノを強め際立たせて。 曲を通して右の旋律と左の伴奏の形があまり変化しないシンプルな形です。 曲の抑揚は細かい強弱とタイミングで表現します。強弱はレベルで考えて。 伴奏もアルペジオ形は下から上に一つにまとめる動きと指使いで弾きます。 強弱や響きのバランスを決めて曲を完成に近づけて行きましょう。
続きを見る »最新投稿
奏法 クレメンティ ソナチネ Op.36-2 第1楽章 (1)
#236 マスネ タイスの瞑想曲 (1)
マスネ作のオペラ「タイス」からお馴染みの名曲のピアノ編曲版です。 オリジナル版のバイオリンのようにピアノを旋律的に歌わせて弾きましょう。 テンポ速めの昔とゆっくりの現代のバイオリンの演奏を参考に学びましょう。 まずは2段を学びます。タイミングと引っ張るタッチ、伴奏とのバランスに注意。 強弱の付け方を意識してラレファシと上へ向かってクレッシェンドします。 自然な強弱で上向きのフレーズはcresc、下降やフレーズの終わりはdimで。 メロディーは強弱よりタイミングを意識。バイオリンのルバート感を参考に。 タイミングは強弱と同等以上に大切に考えます。正確さより自由なリズムで。 旋律は硬くならずにバイオリンに負けずに自由に豊かに美しく歌いましょう。 伴奏を弾きながら実際にメロディーを歌ってタイミングを確認するのも可。 注意すべきことは長い音を前の音と比較して強弱を確認しましょう。 長い音をビブラートできる弦楽器の特徴をうまく表現できると良いです。 左手がフラットにならないよう強弱を大切に。 実際にバイオリンの音色や弾き方をイメージして真似てみましょう。 弦楽器のようなスムーズなレガートを心がけて弾いてみましょう。
続きを見る »#235 グリーグ 抒情小曲集「昔々」(2)
抒情小曲集「昔々」の続き、テンポの速い民族舞踊の部分を学びます。 生き生きと、付点2分音符が前の部の4分音符の速さになる2倍速テンポです。 「飛び跳ねる舞踊」のイメージで表記のとおりに。左は5度で鳴る民族楽器。 アルトは打楽器のようにリズムを取って。緑の印は少しテンポを緩めて。 右手の連打のリズムはアクセントとテヌートで足音を踏み鳴らすように。 ppとありますが強弱変化とタイミングでリズムを柔軟に感じましょう。 ペダルは伴奏に合わせて踏み替え、濁らないよう離すタイミングに注意。 タイミング、アクセント、強弱、ペダルを好みに合わせて組み合わせて。 H-durへの転調は少し大きな強弱と勢いで表して後の表現は同じように。 調性はe-mollで始まりE-dur→5度上のH-dur→5度+半音下のes-moll→ 5度上のb -moll →5度上のf-moll→5度上のc -mollへ。 和音はI-IV-I-V と進み、Vを短調にした和音がIになる短調へ転調しています。 全て5度の関係で転調している事を知れば曲の理解に役立ちます。 調によって優しく、明るく、鋭くなど響きを変化させ最後は必ず小さく。 クレッシェンドして山場に近づき、ヘミオラのリズムで更に盛り上がります。 123-123のリズムが12-12-12と下から上の活発なタッチでritしながら。 この先はdownで重いタッチで、左手2拍目にアクセントで民族調に。 この転調部はゆっくりテンポを落として強弱も一緒に練習しましょう。 歌に戻って行く部分は段々テンポと勢いを落として。 曲を通して民謡と舞踊のコントラストを表現しましょう。
続きを見る » ムジカ・フマーナ オンラインスクール
ムジカ・フマーナ オンラインスクール